

茶碗蒸しは嫌いだ、という人がいるのだろうか。僕は、何故か茶碗蒸しが大好物である。最近のファミリーレストランなどの外食屋さんで出てくる茶碗蒸しは、湯のみ茶碗程度の小さなサイズの蒸し茶碗であることが多い。また、京会席料理などで接待されるときに出てくる茶碗蒸しも同じように小さいものが多い。しかしながら、このサイズの茶碗蒸しは、「本来の大きさ」では無いと僕は確信している。
少し話は、ジャンプしてしまうが、18年間生まれ育った滋賀の実家の村では、冠婚葬祭の度に、その宴席では、地元の仕出し料理屋から料理膳が運ばれてくることがほとんどであった。今では遥か昔の懐かしい思い出であるが、お嫁入りの「立行(たちぎょう)」と「嫁貰い」儀式の祝宴の時などは、村中上げての大儀式だったような記憶している。「立行」とは、娘を嫁として他家へ送り出すほうの儀式である。これら宴席では、2、3日ぶっ続けの宴会があり、何回も祝い膳がその家で出された。僕も、小学校のとき、何回か村、親戚の家へ「御よばれ」したことを記憶している。お葬式も、悲しみごとの行事ではあったが、若い人の葬式ではなく老人のお葬式は、悲しんでいるのはその家の家人だけで、村の衆が全体で運営するその葬儀は、はっきり言って、仏事であっても祝宴と何ら変わらぬものであった。村の鎮守のお宮さんのお祭りも含めて、こうして、僕の小学校時代の村での冠婚葬祭行事は、村の衆とその近隣の村の人も含めて唯一の社交の場であり、お酒の宴席であったのである。

したがって、この冠婚葬祭が、かなりの頻度で各村々、各家々でそこかしこであったため、仕出し料理屋さんは、結構商売になっていたはずである。僕の生まれ育った故郷に「野瀬」という村があり、ここに「つるや」という仕出し料理屋さんがあった。僕の家で冠婚葬祭があったときは、必ずといっていいほど父はこの料理屋から膳をとって村や親戚のお客様をもてなしていた。料理は、焼き物やお刺身などこれといって珍しいものはなかったが、後でこれはこの地場しかないものであると気がついたものが、「鯉の刺身」であった。一度、会社の友人が実家に来てくれたとき、それをご馳走したことがあったが、他では食べられない珍味であることをこのときに知った。

さて、その宴席の膳に必ずといって良いほど有るのは、「茶碗蒸し」である。ただし、その当時その膳の上に乗る「茶碗蒸し」の大きさは、冒頭述べたような、小さな茶碗蒸しサイズではなかった。少なくともあの3倍のサイズ(茶碗の直径10cm)はあった。その茶碗蒸しは、その料理屋から仕出しされたこともあったのかも知れないが、その多くは、その家の蔵などから出してきた先祖伝来の茶碗蒸し専用の茶碗を使ってのその家直轄の料理だったような気がする。僕の実家も、その宴席があるときには、母が茶碗蒸し茶碗を蔵の二階から下ろしてきたように記憶している。その宴席の当日は茶碗蒸し料理をするために家のカマドで朝から湯を滾らせて蒸すのである。サイズが大きいので一度に全員分はできないが、蒸し器を何段も重ねて近所から助っ人で来ている女性陣が蒸していたような気がする。今から思い起こすと大変な仕事だったはずだ。

茶碗蒸しが何故、好物なのかを分析すると、あの黄色く固まった玉子生地のだし汁の中で海老や蒲鉾などの具が最初は表面に少しだけ顔をのぞかせているのだが、「次にどんな具が出てくるのだろう」、という新鮮な期待の気持ちで子供心にその味とともに茶碗蒸しが好きになっていったように思い返す。
そんな懐かしい茶碗蒸しは東京の方に来てから、あの田舎のサイズの茶碗サイズにはもうお目にかかれないと思っていたが、銀座8丁目の「吉宗」という店の噂を初めて聞いて行った事があった。「吉宗」という店の名を「よしむね」と言ったら、店員から「よっそう」と読むこと教えられたように記憶している。
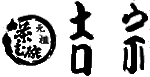
随分と繁盛している様子で、暫く入り口で待たされた。茶碗蒸しだけでお腹が一杯になるという、その吉宗の茶碗蒸しは、その茶碗を眼前に見るまでは信じられなかった。茶碗蒸しは確かに丼サイズで、あの懐かしい実家での蔵から出てきた茶碗蒸し茶碗のサイズよりも少し大きかった。その吉宗の茶碗蒸しを満喫したあと、僕は昔の実家の宴席での茶碗蒸しのサイズを思い浮かべていた。いまでも時々、銀座八丁目の吉宗のお店の前を通りかかると、あのビックサイズの茶碗蒸しと実家の宴席で頬張った茶碗蒸しの味を懐かしく思い出すのである。 (平成15年4月6日記)
【注釈】吉宗の創業は1866(慶応2)年、長崎市万屋町(現在の浜町)で初代・吉田宗吉と言う人が「吉宗」の屋号で、茶碗蒸し、蒸し寿司専門の店を創業したのが始まりだそうである。独自の手法で調整しその素朴な庶民の味は百三十余年経った今も親しまれている。茶碗蒸は丼としてだしており、卵とだし汁がたっぷり使われていて、さっぱりしているから量が多くても全然飽きない。白身魚、鶏肉、しいたけ、きくらげ、たけのこ、ぎんなん、あなごなど具も丼いっぱいでである。 1970(昭和45)年には、東京でも本場長崎の味を、ということで銀座に開店したそうで銀座八丁目のお店の他に信濃町駅前にもお店がある。長崎の郷土料理の、皿うどん、長崎ちゃんぽんのほか、さらし鯨(鮪でいえば大トロの部分)や鯨尾の身(鯨の尾のひれの部分)などの珍しい鯨料理も出している。

