

集中豪雨により相次いで河川が氾濫し甚大な被害をもたらしたが、一方で今年は記録的な連日の猛暑が続いた。降れば集中豪雨、降らなければ、異常渇水。日本ほど多彩で極端に走る自然災害の国は無いだろう。台風などの印象から、日本の夏の降水量は多いように思うが、他国と比べると統計学上、日本は渇水国なのだそうだ。関東地方にも平成6年には利根川水系の異常渇水により断水騒ぎがあった。夏の異常渇水になると、最も深刻な影響を受けるのは、お米を作っている農家であろう。今回のエッセイは、日照りの季節になる度に思い出す「夜叉ヶ池(やしゃがいけ)」の紹介である。

私が学生時代の頃、実家のある北近江地方は猛烈な異常渇水になったことがあった。付近の河川は全て干上がり、田んぼに水が殆ど来なくなった。最も水を必要とする稲穂の生育時期に水がなくなってしまうと農家は死活問題であり殺気立った。僅かな小川の水を奪い合うために、連日徹夜の「水番」が立った。この文明社会でも渇水の異常事態の中では、昔ながらの決め事が幅を利かせていた。結局、この年のお米の作柄は良くなかったはずだ。この様な異常渇水が数十年に一回の頻度で発生するらしいが、そのためか氏子になっている地元の神社の祭りには「雨乞い」太鼓踊りが伝統芸能として伝わっていた。その昔は日照り続きの年になると、この太鼓踊りを神社へ奉納し、雨乞いをしたという。この雨乞い踊りの奉納でも「効き目」が無いほどの強烈な日照りの年には、滋賀県、福井県、岐阜県の三県境の深山に位置する「夜叉ケ池」にまで赴き、太鼓踊りを奉納し「雨を降らしたもう」と雨乞いしたという。

坂東玉三郎が主演の映画にもなった泉鏡花の戯曲「夜叉ケ池」で御存知の方もいらっしゃるかも知れないが、夜叉ケ池は、岐阜県の大河である揖斐川の源流、三国岳と三周ケ岳間の山頂付近に位置している。標高1100mを越える山頂付近に位置しているにも拘わらず、決して水が枯れた事がない神秘の池なのだ。「夜叉ケ池」には1200年前から伝わる「龍神」伝説がある。地元の雨乞い踊りの伝統芸能に関連して、父からその夜叉ケ池の伝説を聞いていた。

その大渇水の翌年、お盆休みに帰省した兄と共にこの夜叉ケ池に一度登ったことがある。夜叉ケ池への登山は、岐阜側からの登山道が一般的だが、北側の福井県今庄町からの登山道も存在する。広野ダムの登山口までは車で行けるかが、そこからは人一人がやっと通れる狭い山道が続く。8合目付近までは、比較的登りやすいが、そこからは険しい岩山の道である。息を切らせて、歩くこと約1時間半、やっとのことで登り詰め、ぱっと一面に開けたところに、その夜叉ケ池があった。額に汗して登り詰めたことの反動からか、凛とした雰囲気の中で池には澄み切った水が満々と貯えられていてとても荘厳な感じがした。池の外周は約540m。周りは、もちろん樹木に囲まれているが、日本庭園によく見られる回遊式の池の様に整然としていてとても深山の池とは思えない。これは後から聞いた話であるが、池に棲む龍神が時々池の周囲の葉刈りをしているそうだ。この時は、既に陽が傾いた時刻とあって他に登山者も無く、あたりは静けさだけが漂っていた。雨乞いに訪れる登山者は、龍神に嫁いだ夜叉姫へのお土産にと、持参した白粉や紅などを戸板に乗せて池に浮かべるといつしか渦が巻き起こり吸い込まれていくそうだ。龍神が、池から現れ出ないかと暫く兄と二人で池の畔に佇んでいたが、この時はお目に掛かれなかった。
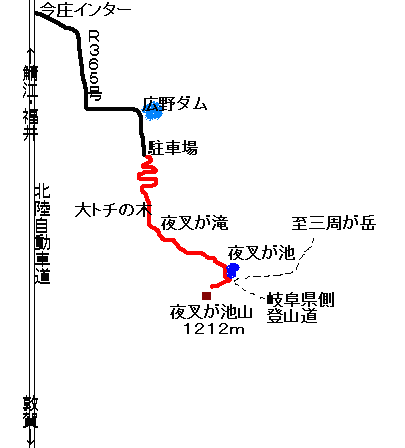
1200年前の大渇水の年に、雨乞いの願いを聞き入れてもらった龍神に夜叉姫を嫁がせたという岐阜県安八郡神門の安八太夫の子孫は代々その家が続いていて、渇水の年になると今でも龍神への雨乞いの仲介役として役割があるそうだ。毎年8月16日には、龍神祭りが催されている。神秘の池「夜叉ケ池」にもう一度登ってみたい。■ (平成16年9月記、平成27年9月10日編集)

